この記事にはプロモーションが含まれます。リンクから購入されると筆者に報酬が発生します。
「失敗をどう扱うか」で、その後の成長は大きく変わる。
そんなことを教えてくれる本が『失敗の科学』(マシュー・サイド 著、有枝春 訳)です。
航空業界や医療現場の事例を通じて、失敗を隠すのではなく“データ”として改善につなげる重要性を解説しています。
失敗は誰にでも起こるものですが、それを恥じて隠すか、正しく分析して未来に活かすかで、結果は大きく変わります。
この本を読んで、自分のこれまでの考え方を大きく見直すきっかけになりました。
今回は、私自身がこの本を読んだ目的や学び、そして感想をまとめてみました。
勉強や仕事で失敗を繰り返してしまう人、努力しているのに結果につながらないと悩んでいる人に、ぜひ読んでほしい一冊です。
読む目的
私はよく大小さまざまな失敗を繰り返し、そのたびに自己嫌悪に陥っていました。
努力したのに結果が出ないと「自分はダメだ」と感じてしまう…。
たとえば、資格の勉強をしていても「こんなに時間を使ったのに解けない」「毎日続けているのに成果が出ない」と落ち込むことがよくありました。
ランニングや筋トレでも、思ったように記録が伸びないと「やっぱり自分には向いていないのでは」とネガティブに考えてしまいます。
そんな自分を変えたくて、「失敗から何を学ぶべきか」を知りたいと思い、この本を手に取りました。
学んだこと
1. 進化のカギは「失敗との向き合い方」
失敗は終わりではなく改善のチャンス。
失敗から学び、システムを変えることで前に進めます。重要なのは「同じ失敗を繰り返さない仕組み化」です。
- 例:貯金ができない → 給料の10%を自動的に貯金口座へ振り込む。
- これなら意思の力に頼らず、自然に貯金がたまっていく。
このように“仕組み化”は仕事や勉強にも応用できます。
朝活が続かないなら、夜のスマホ時間を制限して早く寝る仕組みを作るなど、自分を助けるルールを設計することが大切だと気づきました。
2. フィードバックがなければ努力は空回り
ただ努力を重ねても、間違いを指摘してくれる仕組みがなければ成長できません。
人は自分の弱点を過小評価したり見落としたりしがちです。
- 例:インプットばかりの勉強 → 問題を解いてアウトプットし、どこでつまずいたかを確認する。
私自身、中小企業診断士の勉強をしていて「教材を読むだけで満足」してしまうことがありました。
でも実際に問題を解いてみると、理解したつもりの部分でミスが多発。
これでようやく自分の課題が見えるようになったのです。
努力を成果に結びつけるには、必ず“フィードバック”を組み込むことが必要だと実感しました。
3. 「質より量!」完璧主義の罠
「考え抜けば最適解が得られる」というのは誤解。
失敗を恐れて動けないより、実行と修正を繰り返す方がはるかに前進します。
- 例:ブログ記事を書くときも「もっと良い表現があるのでは」と悩んで公開できないより、とりあえず出してみて読者の反応から修正する方が成果につながる。
小さな行動でも数をこなし、失敗を材料に軌道修正することが大事。
完璧主義は一見努力家に見えますが、実際には成長を止めてしまうこともあるのだと感じました。
感想
読み終えて、自分はこれまで「暗闇の中でゴルフをしていた」のかもしれないと感じました。
闇雲に練習して満足感を得ても、フォームや道具、方向性を検証しなければ結果はついてきません。
大事なのは「やり方」と「フィードバック」。
失敗を自己否定に使うのではなく、データとして扱って改善につなげることが必要だと学びました。
この考え方を取り入れると、仕事や勉強の見え方も変わります。
ミスをしたときに「自分はダメだ」と思うのではなく、「改善のヒントをもらえた」と前向きに捉えられるようになります。
そうすれば挑戦に対する恐怖も減り、自然と行動量が増えていくのです。
ボールがどこに飛んだかわからないままでは、次の一打に活かせません。
だからこそ、失敗を恐れず挑戦し、改善を繰り返す姿勢が重要。
そして、質を求めすぎず量をこなすこと、さらに「やり抜く力」が成果につながる分岐点になるのだと思います。
まとめ|失敗は“データ”として活かそう
『失敗の科学』を読んで、失敗は「終わり」ではなく「進化のための材料」だと気づきました。
努力が結果に結びつかないと悩んでいる人にこそ、この本は大きなヒントをくれると思います。
もし「頑張っているのに成果が出ない」と感じているなら、一度立ち止まって失敗を“データ”として分析してみませんか?
それは自己嫌悪の種ではなく、未来への地図になるはずです。
私自身も朝活や資格勉強、ランニングに取り組む中で、数えきれないほどの失敗をしてきました。
でも、そのたびに「原因を探し、改善する」姿勢を持ち続ければ、確実に成長していける。
そう信じられるようになったことが、この本を読んだ一番の収穫です。
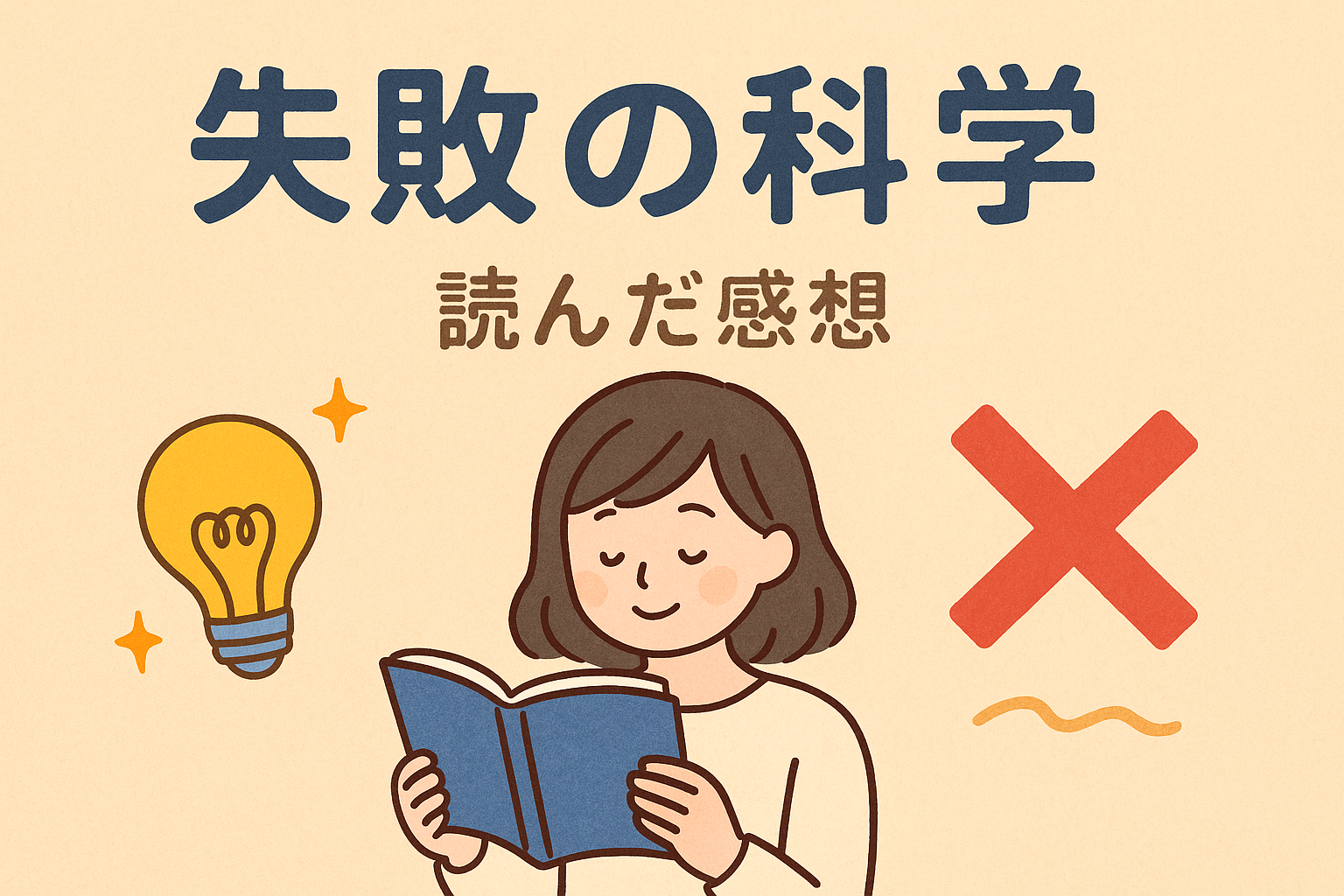


コメント